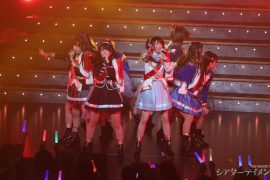Wordless×殺陣芝居「独鬼~hitorioni~」の合同取材会が、6月19日に東京都内で実施、大熊隆太郎(代表・役者)、竹村晋太朗(殺陣・演出・脚本)、西分綾香(劇団制作・役者)が取材に応じてくれた。
大熊隆太郎と竹村晋太朗は高校の演劇部時代からの仲間で、お互いのことはよく知っている。当初は稽古場がなく、河川敷での稽古は「夏暑く、冬は寒く」と笑い、やり取りも息のあった良い雰囲気。枚方市で旗揚げし、今年で結成10周年、今回の公演はこの劇団10周年企画の1つ。毎年恒例の3都市ツアーではあるのだが、竹村晋太朗作品は東京・愛知は初、となる。大熊は京都のノンバーバルパフォーマンス「ギア-GEAR-」では、マイムパートを担当。しかし、壱劇屋はノンバーバルパフォーマンスではなく、「身体表現がメイン」と言い、あくまで“Wordless”を掲げる。「No Word、台詞がないだけで他の芝居とは変わらない」という。こういったところに壱劇屋のこだわりを感じる。つまりフィジカル表現、しかも人の感情、エモーショナルな部分、そこから体が動く、という発想。「人間の行動原理に沿っていれば必要最低限の表現で伝わる」と竹村は語る。つまり殺陣も気持ちが高ぶる、高じていき、そこで初めて「斬る」という行動に出る、ということ。「殺陣は感情表現として有効」と竹村。この「独鬼-hitorioni-」は、“Wordless”作品としては9作目にあたり、死なない鬼が人間の赤ちゃんを拾い、育て、その子が死ぬまでを描く。鬼の感情は“無”。「歳をとっていく女と、行動を共にする人間の男の役を4世代に分けているので、各年代の役者の持ち味が出るのも魅力」とコメント。
また“Wordless”なら物語はどうなるのか?といった疑問も沸くが、普通に台詞がある芝居以上にストーリー性を重視。かといって大袈裟な芝居はしない。無駄なところをとことんそぎ落とす。舞台写真を見る限りでは素舞台に近い。「美術も象徴的なものだけですし、映像を使えば説明が簡単になりそうな場面も、すべて人間が演じています」と語る。つまり、徹底したアナログ表現。さらに「劇団なのでよそにはない表現」とオリジナリティを強調。台詞がないので、当然のことながら台本にはもちろん台詞など書かれているはずもなく、西分綾香は「慣れるまでは大変だった」と笑う。しかし、慣れてしまえば方向性も見えてくる。「わかってくると楽しい」と語る。
2017年の5カ月連続で上演された5本の“Wordless”作品「五彩の神楽」シリーズについては「客席から観たらものすごい段取りの量に!」と西分。大熊は「言葉から解き放たれているぶん、そのときの空気をより感じることができる」と言う。多分、これこそが演じる側の最大の醍醐味なのかもしれない。
“Wordless”作品の特徴、超エキスパート集団“アクションモブ”の存在が大きい。「殺陣に特化した部隊」と大熊。つまり戦いのシーンにおいて、やられては出てきてを繰り返す。公演回数が多ければ多いほどに鍛えられる。竹村も「どんどん進化して、処理速度も速くなり、できることが増えた」と笑顔。また「映像を超える効果がある」と言う。そんなアクションモブの働きぶりも注目 ポイント。

観客の反応については、大阪旅行ついでに来場した外国人観光客のお客様がいたそうで、終演後に「excellent!」と声を掛けられたそう。また、始まって5分で感極まって泣いた方もいた様子。言葉を使わない分、捉え方は自由といえよう。
また「独鬼-hitorioni-」についてであるが、東京から白髪混じりのお客様が遠征して観劇したそうで「昔、お母さんをおんぶして歩いたことを思い出しました」と言われたそう。制作冥利に尽きる言葉であろう。
「演劇の文化は地域によって違う」と竹村。とは言うものの、きっと地域も国境も超えられるかもしれない。7月の東京公演も楽しみであるが、それ以上に20周年を迎える頃にはどのくらい進化するだろうか。


【概要】
劇団壱劇屋「独鬼-hitorioni-」
東京公演: 2018 年 7 月 12 日(木)~7 月 17 日(火) 池袋・シアターグリーン BOX in BOX
愛知公演: 2018 年 7 月 28 日(土)~7 月 29 日(日) 名古屋市東文化小劇場
公式HP:http://ichigekiyaoffice.wixsite.com/ichigekiya
文:Hiromi Koh